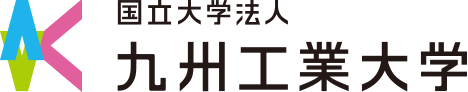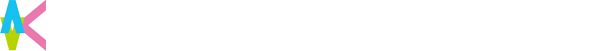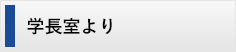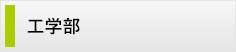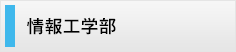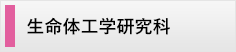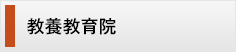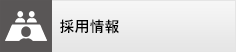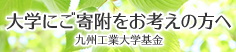主観を科学する:吉田香准教授「感性情報処理」の歴史と応用を解説
- 人工知能学会誌「私のブックマーク」にて、人間の感覚とAI技術の融合を探る-
国立大学法人九州工業大学 大学院生命体工学研究科の吉田香准教授が、人工知能学会誌『人工知能』2025年1月号(Vol.40, No.1)の「私のブックマーク」コーナーにて、「感性情報処理」に関する解説記事を執筆しました。下記では、人間の「主観」を情報技術に取り込む感性情報処理の意義や歴史、そして関連分野を詳細に紹介しています。
■感性情報処理の歴史と進化
感性情報処理は1990年代にその概念が提唱されました。当時は心理学や人間工学を基にしたプロダクトデザインが中心で、人間の感覚や感情を数値化する技術が注目を集めました。その後、2000年代にはこれらの技術が拡張され、特に製品設計やユーザーエクスペリエンスの分野で活用されるようになりました。2010年代以降はAIやビッグデータといった先端技術と融合し、リアルタイムで感情を解析するシステムや、個別化されたサービスの提供が可能になりました。現在では、エンターテインメント、医療、交通、教育など、さまざまな分野での応用が進んでいます。
■情報技術の進化における位置付け
感性情報処理は「情報」という言葉を含んでいますが、情報技術の進化は次の3つの段階で特徴づけられます。
| 1.情報の表現 (1940年代?) |
シャノンの情報理論が確立され、情報を定量的に扱う方法が確立。 |
| 2.情報の意味 (1980年代?) |
人工知能やエキスパートシステムの研究が進み、情報の解釈に焦点が移行。 |
| 3.情報の価値 (1990年代?) |
感性情報処理が登場し、情報を人間の感覚や感情に基づいて扱う試みが本格化。 |
このように、感性情報処理は、それまで客観を志向してきた情報処理から、主観も対象に含むという挑戦的な取り組みの先駆けであったと言えます。
■ 記事中の章構成
吉田准教授の記事では、以下のような章立てで感性情報処理の全体像を解説しています。
1.関連する学問分野
感性情報処理が心理学や認知科学、人工知能などさまざまな学問分野とどのように結びついているかを解説。
2.感性情報処理技術に基づく情報システムデザイン
感性データを活用したシステム設計の方法や、それがどのように実社会で役立つかについて具体的な例を紹介。
3.感性情報処理に関連する学会など
国内外の学会や研究グループの活動、感性情報処理の国際的な研究動向を紹介しています。
■ 人工知能学会誌『私のブックマーク』について
『私のブックマーク』は、人工知能学会誌『人工知能』の人気コーナーで、各分野の専門家が注目するテーマの背景や展望を紹介します。詳細は以下リンクをご覧ください。
◇ https://www.ai-gakkai.or.jp/resource/my-bookmark/my-bookmark_vol40-no1/
■ 吉田香准教授のコメント
「わたしたち人間の主観的な特性である『感性』を科学的に捉え、それを技術に活かすことは、現代社会において極めて365体育appな挑戦です。本記事では、感性情報処理の歴史、関連学問分野とのつながり、そして実用化の可能性を丁寧に解説しました。この研究分野に触れることで、新しい技術や研究の方向性を考える一助になれば幸いです。」
■ 吉田香准教授の略歴
通商産業省工業技術院電子技術総合研究所(現在の国立研究開発法人産業技術総合研究所)実習生、日本学術振興会特別研究員を経て、九州工業大学情報工学部電子情報工学科助手。2000年度IPA未踏ソフトウェア創造事業プロジェクトに採択、2013年4月より現職。博士(工学)。スタンフォード大学CSLI客員研究員、メディア教育開発センター共同研究員、ATRメディア情報科学研究所客員研究員、米国Texas A&M University 非常勤講師、一般財団法人ファジィシステム研究所主席研究員を歴任。感性情報処理、ヒューマンコンピュータインタラクション、ソフトコンピューティング等の研究を行っている。IEEE、日本感性工学会、日本知能情報ファジィ学会、バイオメディカル?ファジィ?システム学会、人工知能学会、情報処理学会会員。